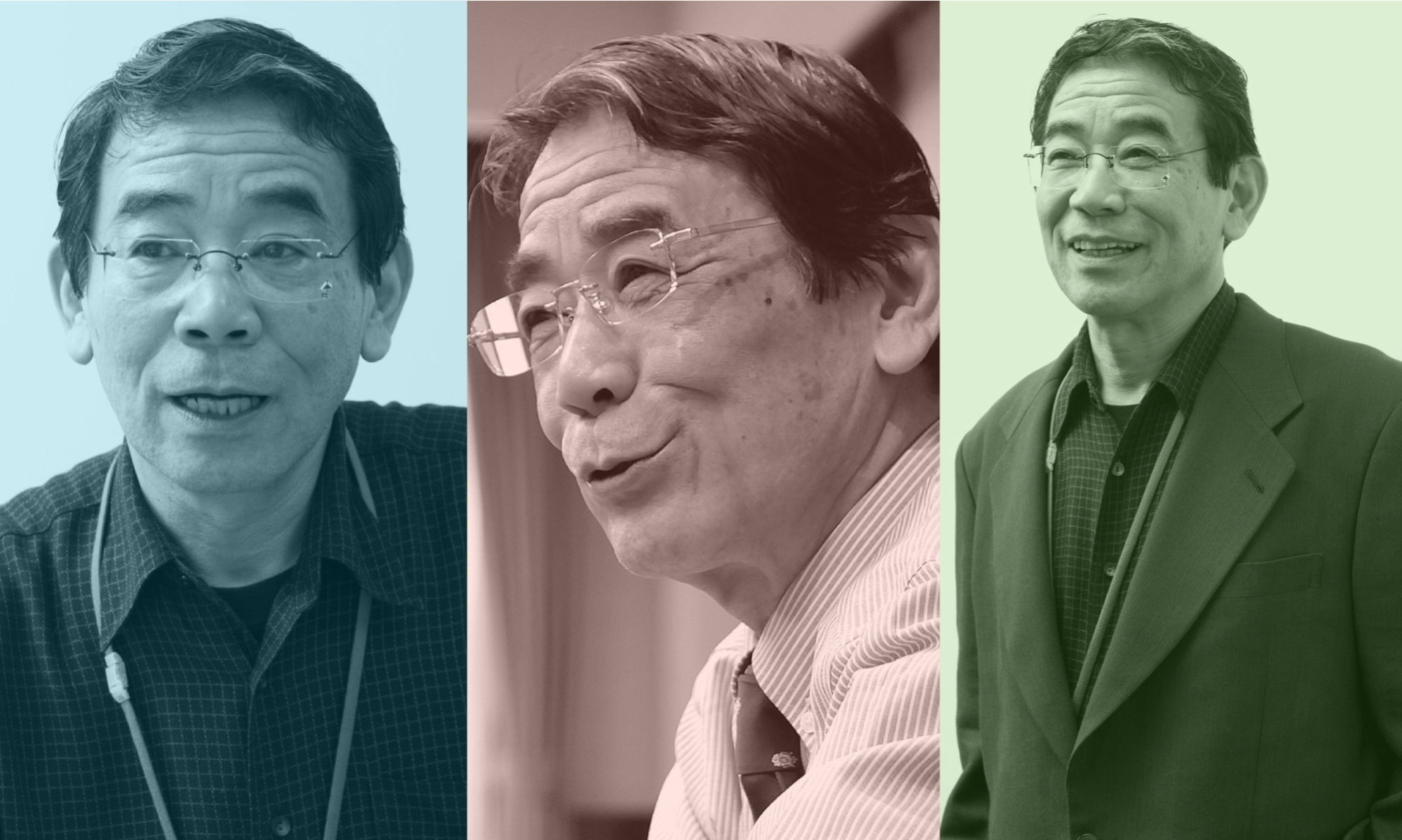渡辺利夫の署名記事や対談・講演録、関連記事などです。各記事タイトルをクリックすると閲覧いただけます。
最新の論説
テーマ:心
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2020年10月10日 | 文明之虚説35 放哉と山頭火 | Voice11月号 |
| 2019年9月10日 | 文明之虚説22 種田山頭火 | Voice10月号 |
| 2018年8月10日 | 文明之虚説9 人生百年時代? | Voice9月号 |
| 2017年12月9日 | 文明之虚説1 癌はどういう病か | Voice1月号 |
| 2017年6月19日 | 正論 高齢者がん治療方針を転換せよ | 産経新聞 |
| 2017年1月11日 | 正論 超高齢化社会をどう生きるか | 産経新聞 |
テーマ:コロナとどう付き合うか
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2020年9月1日 | コロナ時代をどう生きるか-高良武久先生の著作に親しもう | 生活の発見10月号 |
| 2020年8月10日 | 文明之虚説33 防衛単純化の機制 | Voice9月号 |
| 2020年8月6日 | 正論 不安と恐怖の虜囚となるなかれ | 産経新聞 |
| 2020年5月6日 | 正論 新型コロナ感染不安の心理学 | 産経新聞 |
テーマ:近代史のなかの日本人
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2020年4月10日 | 文明之虚説29 児玉・後藤の検疫事業 | Voice5月号 |
| 2020年3月10日 | 文明之虚説28 人類も亦生物ノ一ナリ | Voice4月号 |
| 2020年2月10日 | 文明之虚説27 西郷菊次郎・隆秀 | Voice3月号 |
| 2020年1月10日 | 文明之虚説26 後藤新平の中の自治 | Voice2月号 |
| 2019年8月9日 | 正論 福沢諭吉「帝室論」の中の天皇像 | 産経新聞 |
| 2018年12月10日 | 文明之虚説13 秋山真之の臨終 | Voice1月号 |
テーマ:台湾
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2020年9月18日 | 正論 李登輝氏の葬儀を前に考える | 産経新聞 |
| 2020年2月17日 | 正論 台湾総統選に映し出された真実 | 産経新聞 |
| 2019年12月23日 | 正論 李登輝氏 二つの政治的決断 | 産経新聞 |
| 2019年3月10日 | 文明之虚説16 台湾人の日本評価 | Voice4月号 |
| 2019年2月10日 | 文明之虚説15 日本の台湾統治 | Voice3月号 |
| 2018年11月16日 | 正論 台湾少年工「2つの祖国」の物語 | 産経新聞 |
テーマ:韓国
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2019年11月28日 | 正論 実証研究『反日種族主義』の衝撃 | 産経新聞 |
| 2019年11月6日 | 正論 「反日韓国 親日台湾」由来は何か | 産経新聞 |
| 2019年9月13日 | 背信違約は彼等の持前にして毫も意に介することなし-福澤諭吉の中の朝鮮 | Hanada セレクション |
| 2018年5月10日 | 文明之虚説6 「自ら家を解く」韓国 | Voice6月号 |
| 2018年4月23日 | 正論 韓国民よ 政治危機に覚醒せよ | 産経新聞 |
テーマ:いい加減にしないか
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2019年10月21日 | 正論「家族の解体」ここまできている | 産経新聞 |
| 2019年10月10日 | 文明之虚説23 受動喫煙防止法 | Voice11月号 |
| 2019年5月10日 | 文明之虚説18 朝日社説の貧相 | Voice6月号 |
| 2018年2月27日 | 正論 広辞苑の台湾記述は誤りである | 産経新聞 |
| 2018年2月10日 | 文明之虚説3 医療思想の貧困 | Voice3月号 |
テーマ:人物
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2020年9月 | 追悼 私の中の李登輝先生 | 日本の息吹10月号 |
| 2019年12月10日 | 文明之虚説25 土屋高徳さんのこと | Voice1月号 |
| 2019年11月10日 | 文明之虚説24 秋田智司君のこと | Voice12月号 |
| 2019年10月10日 | こころにひびくことば「人間は不安の器である」 | PHP11月号 |
| 2017年7月27日 | 正論 「日本精神」の丈夫 蔡焜燦氏逝く | 産経新聞 |
その他いろいろ① 2016~2020年度
その他いろいろ② 2011~2015年度
その他いろいろ③ 2005~2010年度
| 掲載日 | 記事タイトル | 掲載媒体 |
|---|---|---|
| 2010年度(平成22年度) | ||
| 2011年3月20日 | 日本近現代史の地政学的環境と苦難 | 拓殖大学日本文化研究所新日本学 第20号 |
| 2011年3月1日 | 著者インタビュー 『君、國を捨つるなかれ 「坂の上の雲」の時代に学ぶ』 | アジア時報3月号 |
| 2011年1月27日 | 正論中国を踊らす北の「崩壊カード」 | 産経新聞 |
| 2011年1月8日 | 特集 近代史に学ぶ「政治の決断」 | Voice 2月号 |
| 2011年1月8日 | 土曜特集 日本外交の針路 | 公明新聞 |
| 2011年1月7日 | 国家を超える【21世紀と後藤新平 Part4】 | 後藤新平の会会報 |
| 2011年1月1日 | 石井英夫の今月この一冊君、國を捨つるなかれ | WiLL 1月号 |
| 2010年12月30日 | 正論闘争本能失った国と個人を憂う | 産経新聞 |
| 2010年12月30日 | 東アジア共同体幻想と中国の覇権主義 | 超大国中国の本質 |
| 2010年12月25日 | こころ 老いる身体感 失う恐れ | 読売新聞 夕刊 |
| 2010年12月16日 | 日本に対する中露の「瀬踏み」 | 日本の息吹(発行先:日本会議) |
| 2010年12月16日 | 偉大なる日和見主義 | 日本通お国自慢・13の視点 |
| 2010年12月9日 | 週刊新潮 掲示板 | 週刊新潮12月16日号 |
| 2010年12月1日 | 尖閣諸島における中国漁船衝突事件 | 東京商工連盟ニュース |
| 2010年11月14日 | 事実を追って淡々とつづる | 毎日新聞 |
| 2010年11月5日 | 拓殖大学とはいかなる存在か-百年史を編んで- | 海外事情11月号 |
| 2010年10月25日 | 日本の指導者は自国の歴史から外交感覚を学べ | セキュリティ研究 2010年11月号 |
| 2010年10月20日 | 正論中国は遅れてきた帝国主義国家 | 産経新聞 |
| 2010年10月3日 | 時代を読む漁船衝突事件の学習効果 | 東京新聞 |
| 2010年9月10日 | 発展を続ける中国経済の"実像" | 新国策9月号 |
| 2010年8月27日 | 正論 現在の価値観で過去断罪するな | 産経新聞 |
| 2010年8月4日 | 正論 自虐ではなく敗北への自省が必要 | 産経新聞 |
| 2010年7月4日 | 時代を読む 人民元弾力化の背後要因 | 東京新聞 |
| 2010年7月4日 | 書評「日本古代史 正解 纒向時代編」大平裕著 | 産経新聞 |
| 2010年7月1日 | ASEAN統合を促すインフラ支援に注力を | 国際開発ジャーナル7月号 |
| 2010年7月 | 特集1 興隆する東アジアとの向き合い方その経済発展の実像と日本の歩むべき道 | 月刊 都市問題 |
| 2010年7月 | 巻頭言 用語を練るということ | 拓殖大学研究所ガイド2010 |
| 2010年6月17日 | 正論菅政権は日米「8月合意」を守れ | 産経新聞 |
| 2010年6月17日 | 21世紀政策研究所の今後の研究プロジェクトについて | 21PPINEWS LETTERNo13 (21世紀政策研究所) |
| 2010年6月15日 | 今を生きて在る幸せを学生に与えよう | We Believe6月号 |
| 2010年6月6日 | 拓殖大公開講座 渡辺学長が講演 | 埼玉新聞 |
| 2010年5月5日 | 国家主権の諸相について考える | 海外事情5月号 |
| 2010年5月4日 | 正論 鳩山政権を蝕む「反国家」の思想 | 産経新聞 |
| 2010年4月25日 | 時代を読む 恐ろしきポピュリズム | 東京新聞 |
| 2010年4月20日 | 東アジア共同体構想どれだけ非現実的かを証明しよう | WEDGE5月号 |
| 2010年4月11日 | 産経志塾日本は「国家」や「公」の観念再生を | 産経新聞 |
| 2010年4月4日 | 時代を読む 「官僚資本」化する中国 | 東京新聞 |
| 2009年度(平成21年度) | ||
| 2010年3月26日 | 「大陸への関与は抑制的に」産経志塾で渡辺拓大学長 | 産経新聞 |
| 2010年3月25日 | 正論 日米に反感を広げた「密約」検証 | 産経新聞 |
| 2010年2月23日 | アメリカという覇権国家との同盟関係を維持するための必死の努力なくして、日本が独自に存在できるほど世界は甘くない | 財界 3月9日号 |
| 2010年2月16日 | 「産経志塾」受講生募集「産経志塾」募集要項 | 産経新聞 |
| 2010年2月15日 | 正論「陸奥宗光よ、ふたたび」を思う | 産経新聞 |
| 2010年2月1日 | 「私」を超えられない日本人の器 | 月刊 MOKU2月号 |
| 2010年2月1日 | もう一つの国家基本問題 | 国基研だより2月号 |
| 2010年1月8日 | 鳩山政権の外交課題と東アジア共同体構想 | 日本証券経済倶楽部No.502 |
| 2010年1月5日 | 正論「日英同盟」廃棄の轍を踏むな | 産経新聞 |
| 2009年12月28日 | 日本の生きるべき道-海洋同盟か大陸関与か | 『日本をあきらめるな!考える行動する若い力が未来をひらく』 日本青年会議所編 |
| 2009年12月27日 | 人間ドックと病気、渡辺利夫さん語る | 山梨日日新聞 |
| 2009年12月27日 | 新刊紹介『朴 正熙の時代』 | 山梨日日新聞 |
| 2009年12月18日 | 正論 「離米・親中」に舵取りしている | 産経新聞 |
| 2009年12月15日 | 10月15日 新渡戸稲造博士命日前夜祭 | 太平洋の橋 |
| 2009年12月6日 | 陸奥宗光 国益を守るために…カミソリ大臣、三国干渉に立ち向かう | 歴史街道1月号 |
| 2009年11月29日 | 時代を読む 「東アジア共同体」の危うさ | 東京新聞 |
| 2009年11月27日 | この人 "健康幻想"脱却を説く | 東京新聞 |
| 2009年11月18日 | 正論外交に「主義」を持ち込む危うさ | 産経新聞 |
| 2009年11月17日 | 第21回アジア・太平洋賞近現代史の空白 見事に埋める | 毎日新聞 |
| 2009年11月5日 | パル判決の意味をいま考える | 環太平洋ビジネス情報RIM 11月号 |
| 2009年10月29日 | 渡辺拓殖大学長が講演「日米同盟堅持は当然」 | 埼玉新聞 |
| 2009年10月29日 | 正論 国益を見据え「普天間」決断の秋 | 産経新聞 |
| 2009年10月21日 | 「健康」に縛られず生きる 「人間ドッグが『病気』を生む」を出版 | 山梨日日新聞 |
| 2009年10月16日 | 新渡戸の功績しのぶ | 岩手日報朝刊 |
| 2009年10月1日 | 「東アジア共同体」の幻想に惑わされるな | 明日への選択10月号 |
| 2009年9月27日 | 時代を読む 「中国化」する東南アジア | 東京新聞 |
| 2009年9月26日 | 石井英夫の今月この一冊『どうするどうなる日本の活路』 | WiLL 11月号 |
| 2009年9月25日 | 論壇 福澤、陸奥の「理」よ再び | 月刊財界人11月号 |
| 2009年9月11日 | 正論 強大国支配になぜ気づかない | 産経新聞 |
| 2009年8月10日 | 核開発の「工程表」練り上げよ | 産経新聞 |
| 2009年8月1日 | 福澤諭吉 朝鮮近代化への夢と挫折 | 環太平洋ビジネス情報RIM9月号 |
| 2009年8月1日 | 『坂の上の雲』の時代に何を学ぶか-激動の国際社会を生き抜くために- | Monthly IIC8月号 |
| 2009年7月13日 | 正論 個別自衛権が空洞化している | 産経新聞 |
| 2009年6月28日 | 時代を読む 大学の大衆化と学力低下 | 東京新聞 |
| 2009年5月28日 | 今、いちばん厳しい時期にある冷戦崩壊後の極東アジア地域外交 | 月刊世相6月号 |
| 2009年5月1日 | 亡国の危機に『諸君!』の休刊を憂う | 諸君! 6月号 |
| 2009年4月27日 | 同盟とは何か-日英同盟下、戦艦購入についての挿話 | 環太平洋ビジネス情報RIM4月号 |
| 2009年4月19日 | 提言-ニッポン 「公」に生きることの意味伝えたい | 産経新聞 |
| 2009年4月6日 | 正論 中国の内需拡大は成功するか | 産経新聞 |
| 2008年度(平成20年度) | ||
| 2009年3月29日 | 時代を読む 古代史の「空白」を埋めよ | 東京新聞 |
| 2009年3月29日 | 官民一体で飛躍の種育てる | 山梨日日新聞 |
| 2009年3月15日 | 書評『日本古代史 正解』史学研究の現状に憤怒する | 産経新聞 |
| 2009年3月3日 | 正論 驚嘆すべき福澤諭吉の予見力 | 産経新聞 |
| 2009年3月1日 | 中国改革・開放の成果と限界 | 調査月報IRC 3月号 |
| 2009年2月1日 | 高齢社の社会貢献活動 | 国際開発ジャーナル2月号 |
| 2009年2月1日 | いまなぜ脱亜論か | 日台共栄2月号 |
| 2009年2月1日 | 国家と共同体-曽我ひとみさんの再生 | 虹扶桑社通信Vol.11 |
| 2009年2月1日 | 台湾開発における後藤新平 | 後藤新平書翰集 |
| 2009年2月1日 | 大学院の頃-四人の恩師のことを想う | 月刊 財界人第2号 |
| 2009年1月13日 | 2009年 日本の国際協力を展望する | 月刊国際協力新聞 |
| 2009年1月13日 | オバマ新政権と「日米同盟」 | 産経新聞 |
| 2008年12月25日 | 他策なかりしを信ぜんと欲す | 諸君!2月号 |
| 2008年12月1日 | 若者よ! "公"に目覚めよ | 月刊グローバル経営12月号 |
| 2008年11月30日 | 時代を読む「死生観の時代」 | 東京新聞 |
| 2008年11月28日 | 日米同盟の強化必要(山梨政経懇) | 山梨日日新聞 |
| 2008年11月13日 | 第20回アジア・太平洋賞 | 毎日新聞 |
| 2008年11月1日 | 「公」とは何か | 環太平洋ビジネス情報RIM |
| 2008年11月1日 | オバマ氏の安全保障観に疑義 | 月刊グローバル経営11月号 |
| 2008年11月1日 | 隣の国とどう付き合うか~日中・日韓関係の現状と将来 | 中央電気倶楽部月報 11月号Vol667 |
| 2008年10月25日 | 公に殉じた先輩の血と汗と涙を | 東京ふれあいBunBun2008/第4号 |
| 2008年10月10日 | 集団的自衛権の行使を | 東京新聞 |
| 2008年10月6日 | 正論「新 脱亜論」で訴えたかったこと | 産経新聞 |
| 2008年10月5日 | 後藤新平縁の拓殖大渡辺学長が初来水顕彰会員らと懇談 | 胆江日日新聞 |
| 2008年9月28日 | 時代に「逆襲」される中国 | 東京新聞 |
| 2008年9月18日 | 福田和也の闘う時評『新 脱亜論』の示唆するもの | 週刊新潮9月18日号 |
| 2008年9月1日 | 朝鮮半島を「大陸国家」にしてはならない | 諸君 9月号 |
| 2008年9月1日 | 書評 「新脱亜論」 誰を友とすれば日本人は幸福か? | 改革者 9月号 |
| 2008年9月1日 | 日本のODAをどうする | East Asia東亜9月号 |
| 2008年9月1日 | 日本は大陸に関与すべからず | 月刊グローバル経営9月号 |
| 2008年8月31日 | 大学全入時代に新教科書 | 山梨日日新聞 |
| 2008年8月10日 | 中国への援助を評価する | 月刊国際協力新聞Vol167 |
| 2008年8月4日 | 高橋是清の日露戦争-明治官僚の剛胆と運 | 環太平洋ビジネス情報RIM |
| 2008年8月1日 | ODA大国の復権を官民連携から | 国政ひろば8月号 |
| 2008年7月6日 | 近現代史に学ぶ「海洋国家」日本の選択 | 歴史街道 8月号 |
| 2008年7月3日 | 渡辺拓大学長が特別講義 | 産経新聞 |
| 2008年7月1日 | ODAにおける官民連携の重要性について考える | 経済Trend7月号 |
| 2008年6月29日 | 時代を読む 米、対北カードの放棄か | 東京新聞 |
| 2008年6月26日 | 石井英夫の今月のこの一冊 『新 脱亜論』 | Will 8月号 |
| 2008年6月22日 | 書評 『新 脱亜論』 | 産経新聞 |
| 2008年6月 | 胡錦涛訪日は何を残したか | 月刊グローバル経営6月号 |
| 2008年5月12日 | 後藤新平の台湾開発 -日本の「開発学」の原点 | 環太平洋ビジネス情報RIM |
| 2008年5月12日 | 国益を毀損するODA削減 | 産経新聞 |
| 2008年5月 | 台湾人の台湾アイデンティティ | 月刊グローバル経営5月号 |
| 2008年5月 | 病「気」について | 正論 5月号 |
| 2008年4月22日 | なぜ今、新脱亜論が必要なのですか? | 財界 |
| 2008年4月20日 | 渡辺学長と池上彰氏の対談 「国際教育の先駆者として日本と世界の懸け橋になりたい」 | 読売ウィークリー |
| 2008年 | 指導者の豪気-台湾開発のこと | 季刊【もん】2008年春号 |
| 2007年度(平成19年度) | ||
| 2008年3月30日 | 時代を読む李政権 対北政策の成否 | 東京新聞 |
| 2008年3月 | 中国は上海協力機構に何を求めているか | 月刊グローバル経営3月号 |
| 2008年2月1日 | 問題はオリンピック・万博後に出る | 改革者 2月号 |
| 2008年2月 | 李明博氏は盧政権の政策を正せるか | 月刊グローバル経営2月号 |
| 2008年1月4日 | 若人よ、「公」に目覚めよう | 産経新聞 |
| 2008年1月 | 配信【経済底流】 ODA改革-現場重視で戦略的に- | 共同通信社 |
| 2008年1月 | 不鮮明な日本の安全保障論議 | 月刊グローバル経営1月号 |
| 2007年12月8日 | 日中関係の現状と展望 | 公研 No.532 |
| 2007年12月5日 | 山梨総研 創立10周年フォーラム | 山梨日日新聞 |
| 2007年12月2日 | 時代を読むよみがえる後藤新平 | 東京新聞 |
| 2007年12月1日 | 極東サバイバルの掟は、陸奥宗光に訊け | 諸君! 1月号 |
| 2007年12月1日 | 日本の国際協力を創った人たち | 国際開発ジャーナル12月号 |
| 2007年11月19日 | 第19回アジア・太平洋賞 | 毎日新聞 |
| 2007年11月16日 | 台湾近代化なしとげた理由 | 盛岡タイムス |
| 2007年11月4日 | 時標 南北会談とは何だったか | 山梨日日新聞 |
| 2007年11月1日 | 「胡報告」に見る中国の相克 | 産経新聞 |
| 2007年10月31日 | 朝鮮半島とはいかなる存在だったか | 環太平洋ビジネス情報RIM |
| 2007年9月30日 | 時代を読む なぜ旧親日派糾弾か | 東京新聞 |
| 2007年9月10日 | 最近の東アジア情勢-日中、日韓関係を中心として | 第291回中日懇談会報 |
| 2007年9月3日 | 正論極東アジア地政学の中で日本をみる | 産経新聞 |
| 2007年8月25日 | 日本を支える人材作り | 財界人10月号 |
| 2007年7月31日 | 極東アジア地政学と陸奥宗光 | 環太平洋ビジネス情報RIM |
| 2007年7月21日 | タクシン氏招請を実現 | 読売新聞 |
| 2007年7月1日 | 中国を悩ます民工群 | 東京新聞 |
| 2007年7月1日 | 最近の東アジア情勢-日韓、日中関係を中心として | 調査月報 IRC |
| 2007年6月24日 | 正論 ODA予算の激減に歯止めをかけよ | 産経新聞 |
| 2007年6月16日 | 第291回中日懇談会 "対中韓関係 国益見据えて対応を" | 中日新聞 |
| 2007年6月14日 | 奈良「正論」懇話会 | 産経新聞 |
| 2007年6月1日 | 甦る日露戦争の時代 | 諸君! 6月号 |
| 2007年6月1日 | 日豪・日印「海洋国家」連携の強化 | 商工ジャーナル |
| 2007年5月5日 | 時評 北の核にどう対応するか | 山梨日日新聞 |
| 2007年4月18日 | 正論温家宝首相の微笑の裏に何があるか | 産経新聞 |
| 2007年4月1日 | 日本型の協力モデル、アジアに構築 | NICC NEWSVol.7 |
| 2007年4月1日 | 時代を読む 中国 物件法成立の意味 | 東京新聞 |
| 2006年度(平成18年度) | ||
| 2007年3月26日 | 東アジア情勢と日本の課題 | 日本証券経済倶楽部 NO.469 |
| 2007年3月25日 | 国内外での人材育成への課題とは | JICEの30年 |
| 2007年3月23日 | 中国経済の過熱と「地方の暴走」 | 産経新聞 |
| 2007年3月1日 | 福澤諭吉の「脱亜論」に学べ | 諸君!4月号 |
| 2007年2月1日 | 2007、中国経済の展望 チャイナリスクとは何か-マクロ経済の観点から | 月刊 グローバル経営 |
| 2007年1月31日 | 海洋勢力と大陸勢力-東アジア外交の基礎概念 | 環太平洋 ビジネス情報 RIM 2007 Vol.7 No.24 |
| 2007年1月15日 | 正論中国は少子高齢化に耐えられるか | 産経新聞 |
| 2007年1月1日 | 北朝鮮の核脅威が日本を覚醒させる | 正論 1月号 |
| 2006年12月26日 | 書評 『「反日」を超えるアジア』 | エコノミスト |
| 2006年12月24日 | 時代を読む「陸のアジア」 「海のアジア」 | 東京新聞 |
| 2006年12月15日 | ゙国際開発学の父゙としての後藤新平 | 月刊 機 |
| 2006年12月14日 | 正論 「死はお迎え」の死生観を思う | 産経新聞 |
| 2006年12月1日 | 巻頭言高成長持続のインドに注目せよ | 中小公庫 マンスリー 12月号 |
| 2006年12月1日 | 北朝鮮の核保有への対処に怠りなかるべし | 商工ジャーナル |
| 2006年11月16日 | 書評『大地の咆哮 -元上海総領事が見た中国-』 | 毎日新聞 |
| 2006年11月14日 | ふるさとの道と地域再生 | 山梨日日新聞 |
| 2006年9月1日 | 海洋国家連携としての日米同盟 -日本近代史の中の小泉外交- | 日本人のちから |
| 2006年7月26日 | 経済建設や制度づくりなど日本に貢献できることは多い | 財界 |
| 2006年7月23日 | 時代を読む 留学生受け入れ体制の整備を | 東京新聞 |
| 2006年7月1日 | 東チモールの悲劇再び | 日本国際 フォーラム会報 |
| 2006年7月1日 | 対談 中国よ日本人のナショナリズムを揺り起こすな | 正論 8月号 |
| 2006年6月28日 | スクールガイド 挨拶文 | 拓殖大学第一高等学校 2007年度 スクールガイド |
| 2006年6月9日 | リスク大の反日政策 | 琉球新報 |
| 2006年6月6日 | BookReview「失われた十年」は乗り越えられたか | 週間エコノミスト |
| 2006年6月1日 | 東ティモールの悲劇にもう一度目を向けよ | 商工ジャーナル |
| 2006年6月1日 | 学長 巻頭言 "論理的な文章を-吉村昭『光る壁画』から" | 拓殖大学 研究所NOW |
| 2006年6月 | 《古典再読》 『森田正馬全集』 第五巻 | 中央公論 6月号 |
| 2006年5月29日 | 中国現体制の課題と日中関係の将来 | 環太平洋ビジネス情報 RIM No.21 |
| 2006年4月30日 | 成熟示したタイ政治 -21世紀を読む- | 毎日新聞 |
| 2006年4月23日 | 時代を読む 東ティモール独立の傷痕 | 東京新聞 |
| 2006年4月11日 | 公開セミナー「岐路に立つODA」リポート | 世界週報 |
| 2006年4月 | 裏通りの東南アジア -東ティモールを訪れて考えたこと- | Suruga Institute Report (企業経営研究所) NO.94 SPRING |
| 2006年4月 | 東アジアの経済統合と日本の選択 | ふれあい(納税協会連合会)納税月報 臨時増刊) |
| 2006年4月 | 東アジア共同体:「文明の生態史観」から考察する | 海外事情 4月号 |
| 2006年4月 | 日本のODA、各国の自助努力に貢献 | 月刊ODA新聞 4月号 |
| 2005年度(平成17年度) | ||
| 2006年3月27日 | インサイト チャイナどうする日本の「座標軸」、「一党独裁国と価値共有できるか」 | フジサンケイビジネスアイ |
| 2006年3月27日 | 日本のODA、各国の自助努力に貢献 | 日本教育新聞 |
| 2006年3月16日 | 《ひと・立ちばなし》 50万円のガウン | 山梨日日新聞 |
| 2006年3月6日 | 【公開セミナー】 岐路に立つODA | 朝日新聞 |
| 2006年3月 | 母国とは日本語である -「拓殖文化」発刊に寄せて | 拓殖文化文連30号通刊113号 |
| 2006年3月 | グローバリゼーションの時代にあってこそ自国文化へのアイデンティティを強めよ-ドイツ派遣団の諸君に向けて | 拓殖大学麗澤会海外派遣報告ドイツレポート2005 |
| 2006年3月 | ひどい風邪をひいて考えたこと | 三田評論3月号 |
| 2006年2月28日 | 日本の平均的な若者の集う大学のモデルとなりたい | 財界 |
| 2006年2月28日 | 日中・日韓関係の現状と課題 | 参風第114号 |
| 2006年2月26日 | グスマン大統領名誉博士号関連掲載記事 | 読売新聞東京新聞山梨日日新聞その他海外の新聞 |
| 2006年2月20日 | 第3回 国際教育協力日本フォーラムを開催 | 文教ニュース |
| 2006年2月 | 第3回国際教育協力日本フォーラム日本のODA戦略-自助努力支援の重要性- | 講演 |
| 2006年2月 | 「パクス・シニカ」にアジアが屈する日 | 中央公論2月号 |
| 2006年2月 | 国際協力の現場を担う志高き人材を | 正論 2月号 |
| 2006年1月27日 | 愛国教育 影響強い | 東京新聞 |
| 2006年1月15日 | 《新春討論》平成18年の課題と展望 | 日本証券経済倶楽部 |
| 2006年1月 | 「文明の生態史観」と東アジア共同体 | 環太平洋ビジネス情報RIM Vol.6 |
| 2006年1月 | 新春特集アジアを牽引する日中関係の行方を占う | JCECONOMICJOURNAL1月号 |
| 2006年1月 | 普通の国の関係になれないものか | 日本経済センター会報1月号 |
| 2006年12月21日 | 来春開設の拓殖大学大学院国際協力学研究課 博士後期課程 | フジサンケイビジネスアイ |
| 2005年12月5日 | 第17回 アジア太平洋賞 特集」評者・選考委員 | 毎日新聞 |
| 2005年12月5日 | 時代を読む中国農村の貧困と農民流動 | 東京新聞 |
| 2005年11月23日 | ODAは日本外交の源泉 | 東京新聞 |
| 2005年11月10日 | 学長に聞く「拓大改革プラン」 | 拓殖大学学報252号 |
| 2005年11月4日 | 国際協力・国際理解賞コンクール 「学長あいさつ」 | 読売新聞夕刊 |
| 2005年11月 | 東アジアの政治・経済の動きと未来 | (社)企業研究会月刊ビジネスリサーチNo.978 11月号 |
| 2005年10月1日 | 根深い中国の「反日」 | 山梨日日新聞 |
| 2005年10月 | 「国境を越えての共同研究も」 | 広報はちおうじNo.109610月号 |
| 2005年10月 | 中国経済の"光と影" | 潮 10月号 |
| 2005年9月12日 | 日本文化知らずに国際協力なし | 日本教育新聞 |
| 2005年9月 | 分析の深度について考える | 大学時報No.304Sep.2005 |
| 2005年9月 | 創立30周年の祝辞 | 《創立30周年の歩み》APIC (財)国際協力推進協会9月号 |
| 2005年9月 | 《巻頭インタビュー》「愚直なODA」が最後に勝つ | 選択 9月号 |
| 2005年8月29日 | 《直言提言》 争点の絞込み評価/国益考えた外交必要 | 山梨日日新聞 |
| 2005年8月13日 | 「陸のアジア」を牽制し 「海のアジア」として生きる | 週刊東洋経済 |
| 2005年8月 | 東アジア経済統合の現段階 | IRC No.2068月号 |
| 2005年7月17日 | 「公」に生きる心 育成 | 山梨日日新聞 |
| 2005年7月3日 | 時代を読むアフリカ最貧国支援の拡大を | 東京新聞 |
| 2005年7月 | 日本の東アジア戦略 【共同体への期待と不安】 | 東洋経済新聞社7月号 |
| 2005年7月 | 反日デモから見える日・米・中の"三角関係 | 日経WOMAN7月号 |
| 2005年6月28日 | 書評 「中国 経済革命最終章」 | エコノミスト6月28日号 |
| 2005年6月27日 | 国際研究の厚い学問的基盤を活かし開発協力で汗を流す人材を養成する | 教育通信2005June |
| 2005年6月 | あの人に聞く | Squareすくえあ2005 JULY |
| 2005年6月 | 中国反日暴動をどう考えるか | 商工ジャーナル6月号 |
| 2005年6月 | 幻想を吹きとばす反日地政学 | 中央公論6月号 |
| 2005年5月 | 反日暴動の底にあるもの | 人と国土215月号 |
| 2005年4月20日 | 中国「市場化」の矛盾表面化 | 読売新聞 |
| 2005年4月12日 | 投資リスク 再認識を | 読売新聞 |
| 2005年4月3日 | 時代を読む アジア少子高齢化の波 | 東京新聞 |
| 2005年4月 | 韓国の政治状況に思うこと | NIRA政策研究4月号 |
| 〈前年度〉 | ||
| 2005年3月31日 | 無償の環境支援、継続を | 朝日新聞 |